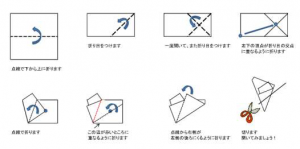休暇の日を書店でぶらぶらと逍遥することほど面白いことはない。
まずは、入り口近くの新刊本から手始めに、
文庫本や新書のコーナーから専門書の類まで
興味をそそる題名が目に飛び込んできたものは片端から手にとって見る。
パラパラとページを繰る。
すかさず書棚に戻すのが常ではあるが、
良書に出会ってしまったら最後、20〜30ページ熟読してしまう始末。
書店の方にはご迷惑をおかけすることには常々反省しきりである。
そして、これぞ、と思った書物に出会えば我が家へ丁重にお連れする。
さて、我が家へお連れしたのは良いが、
「いつかは読むさ」式の「つん読」の世界へ彼は誘われてしまう。
当然のことながら「座右の書」などという高尚な言葉には憧れこそすれ
現実とはほど遠いほど、ひどい本への扱いをしてきた。
我が書棚に埋もれた数知れぬ書籍の呪いも
そろそろ我が身に振りかかる恐れもある。
折角の「読書の秋」である。
新たな心の友を求めて迷いの森へ一歩足を踏み出す。
はて、何にしたものか。
「この一冊」と決め込んで手にすることになれば、
一定期間自らの伴侶として手放す訳にはいくまい。
予想以上のプレッシャーに心の葛藤が高まる。
「運動の秋」「食欲の秋」でもいいではないか。邪念が渦巻く。悶々とする。
と、その時、シャープに一冊の本が視界の中央部に位置した。
それは、講談社学術文庫版『徒然草(一)』である。
本棚ではなく平積みになっていたものだった。
購買意欲をかき立てる書店側の巧妙な本の配置にまんまと引っかかってしまった。
これと言った一冊に出会えず、焦燥の思いが募っていた矢先に
『つれづれ』とは何と皮肉なのだと思いながらも、手は機敏に反応していた。
上手く二元的に機能するものだと感心した。
例の如くパラパラとページを繰る。これはいけると咄嗟に判断した。
どこまで兼好と向き合えているかについては
浅学非才の身には口にしづらいところではあるが、
次の一段はいにしえの書を徹底的に読書することの本質として
心より共感させられる。
「ひとり灯のもとに文をひろげて、見ぬ世の人を友とするぞ、
こよなうなぐさむわざなる。」
(ひとり灯火に書物を広げて、遠い時代の人を友とするのは、
この上ない慰めである。)《徒然草第13段》
徒然草は第243段ある。読破するのはいつのことになるやら。
予定は未定である。