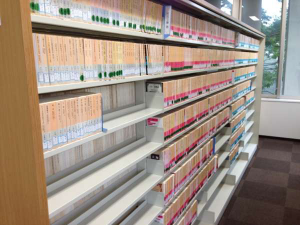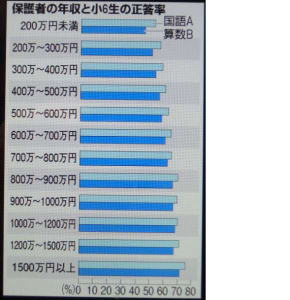さて、話を戻しますと、サーパスでは、話を「聞く」ことが大切であるとしています。
例えば、3、4年生の国語の問題を見ていただくとわかりますが、
(その学年の)選択肢の問題は非常に素直で、傍線部の近くを注意して読むだけでも、
答えが浮き出て見えてくる(イが答えじゃん!というように。)ことが多いと思います。
しかし、傍線部の近くを読んだ→イが答えだとすぐにわかった→◯がついた、という
この一連の流れで、その子の国語力は(塾に来る前より)上がったのでしょうか?
即答できる問題を解いて、それで正解したとしても、実力の確認ができたに過ぎません。
また、パッと見で正解っぽく見えたものに、むやみに飛びつくという癖がつくのも、
よくありません。計算ドリルのような、即答自体を目的としているものはともかく、
なぜそうなるのか?を考えることが大事なものには、それ相応の時間をかけるべきです。
ですから、授業では、イが正解だとすぐにわかってしまうとしても、
選択肢のアとウとエのどこが違うのか、なぜいけないのかを話していきます。
アがいけない理由は、本文のどこに書いてあったのか、どの文の内容と矛盾するのか、
そういったことを話していくのです。
その矛盾する文章は、傍線部のはるか後ろに書かれてあったりするかもしれません。
傍線部の近くしか読んでいなかった子や、
(あろうことか)本文さえ読まずに設問だけ見て問題を解いた子、
そして、答えが合っていたらそれで満足してしまう子は、ここで話を聞かなくなります。
◯なんだからもういいじゃん!と思っているのだと思いますが、そういった子にも
「ちゃんと聞いて!」「集中!」「目を離さないで!」と声をかけるわけです。
参考までに、今週の4年生の予習シリーズの文章は、
『人間と野生動物の付き合い方』をテーマにした文章でした。
文章に登場する例は、1993年の矢ガモ事件でしたが、
その授業で、問いを解くだけ(問題の解き方を教えるだけ)なら味気ないと思います。
この文章を題材にして、どのように話を広げるか。
マニュアルのカッチリ決められている塾なら、
個人の裁量による授業構成は(ベテランの先生以外)認められないと思いますが、
好きに話を広げていいなら、ここに先生のカラーが出るように思います。
例えば、「野生の生き物には~えさを与えてはならないのです。」
という一文が本文中にありましたが、
今なら、熊の話などは、子どもでもニュースで見ていて馴染みがあるかもしれません。
文章中に熊は出てきませんが、そうやって話を広げることで、
文章の理解が深まる可能性は高くなりますし、
カモだけに限定された話ではないことにも気づけるかもしれません。
話を「聞く」ことで、視野が広がり、深みが増すのです。