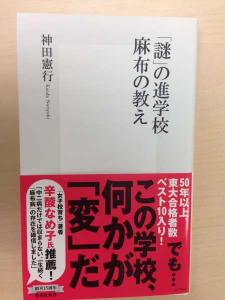自宅の車庫の屋根に柿が一つのっていた。
ベランダから辺りを見回しても柿の木は一本もない。
実を放り投げるような悪ガキも見当たらない。
何の根拠もない存在の存在。
秋晴れに広がる不可解な事実。
そそくさと身支度を済ませ、とにかく道を歩きたい気分になった。
最寄りではない駅まで遠回りすることが解決策ではないことはわかっていた。
けれども今は、わからないことに身を浸らせなければならない。
道の途中に刈田が広がっていた。
もはや実りのない青い単子葉が切り口から生をほとばしらせていた。
田の脇の小畑では柿の木が数十ひしめき合っていた。
小枝には六つから十ほどの柿がたわわに実っていた。
たわわ
この言葉を初めて発した太古の民の口元に想いが馳せないものか。
枝先は柳のように垂れ下がり、最早しなる勇気もない。
自己犠牲にも似た重力への忠誠。
突然、枝先が鞭のように空中へと跳ね返った。
柿の実は、お手玉のように跳ね上がり、雲ひとつない青空に吸い込まれていく。
枝先はバイバイとでも言いたげにいつまでも振動を止めなかった。
ここは道だ。
歩みを止めてはいけない。
駅への一歩を踏み出そうとした。
と、その刹那、熟し切った柿の実が足下に広がっているのに気づいた。
危うく踏みそうになった。
柿の実は見事なまでに形を失っていた。
一体どれだけの重みを吸い込んだのだろう?
もしかして…。
乾いた陽射しが遠くのススキをきらめかしていた。
秋の暮色を身に纏った赤い実が夕日の到来を待ち焦がれていた。
モンシロチョウが頭上を掠めていく。
風の通り道をなすがままに歩んでいるようだった。
柿の実がどこにあってもおかしくない気がしてきた。