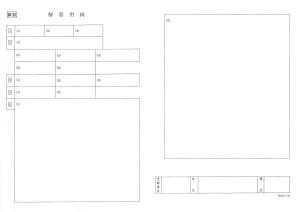「もう一度繰り返していいか?」
この言葉を最後に、プチリとアナウンサーの声がラジオから途絶えた。
あれからもう20年になる。
1993年とその翌年にかけて、
私は、1987年のソ連旅行から数えて6年ぶりにロシア渡航を果たした。
8月下旬、大学のロシア語サークルの後輩たちと共に、
新しく生まれ変わったエリツィン大統領下のロシアとの
邂逅(かいこう)を待ち望んでいた。
しかし、そこで待っていたのは希望のロシアではなく、「混迷のロシア」であった。
当時のロシアでは、急激な資本主義化の結果、経済が混乱し、
ハイパーインフレの最中にあった。
私がモスクワで生活を始めてまず取りかかったこと、それは、
ドルとの交換比率がお得な両替店を市街地に見つけ出すことだった。
なにしろ毎日恐ろしくレートが変動する。
旧ソ連時代には1ルーブル250円ほどであった紙幣が、
なんと1ルーブル0.086円にまで落ち込んだのである。
おかげで外国人である私はその恩恵に浴し、
天下のボリショイ劇場でオペラを500円で鑑賞し、
チェーホフ全集も1200円で購入した。
演劇やバレーを毎日のように観てまわったにもかかわらず、
1ヶ月の生活費で1万円を超えることはなかった。
金銭的には全く困らなかった反面、拙い語学力は滞在中ずっと自分を苦しめた。
ロシア訪問の目的が形式上修士論文の資料集めとなっていたので、
大学関係者に指導教官をお願いしてあった。
幸か不幸か、モスクワ大学の教授に個人指導していただけることとなったのだが、
当然ロシアの専門用語を聞き取れるはずはない。
そこで、情けないことではあるが、通訳の方をつけていただいた。
柔和な表情の方であったが、
日ソ外交交渉の場でも活躍された経歴のジェントルマンであった。
今このように思い返すだけで、浅学非才の当時の自分が蘇り、羞恥が極まる。
当時の講義内容はテープに録音し保存してあるが、
きっと聞き返す機会は来ないであろう。
その通訳の方は、ウォッカの国民ロシア人には似つかわしくなく、
酒を嗜まなかった。
しかし、ただ一度だけ、モスクワ大学の中庭で待ち合わせをしていた際、
彼は真っ赤な表情でやって来た。
「すみません。今日だけは許して下さい。友人がひとり死んだのです。」
彼はそういうと、目頭を赤くにじませた。
1993の9月下旬。ロシアでは「ザラタヤオーシン(黄金の秋)」の季節を迎え、
急速な冷え込みの中、街路樹は鮮やかな秋の色彩で町を彩っていた。
ところが、政治状況は緊迫の度合いを強め、
エリツィン大統領(クレムリン=大統領府)とハズブラートフ議長率いる
議会派(ホワイトハウス=国会)との間で深刻な対立が生じ、
一触即発の様相を呈していた。
そしてついに、十月初頭、議会派がテレビ塔を占拠し内戦が始まった。
大使館からは国外退去の準備指示が入る。
首都モスクワを目指す戦車の列が幹線道路を通過するのを
大学の寮の窓越しに見かけ、今まで経験したことのない非常事態に
背筋の寒さを感じた。
翌日、若気の至りで危険をおかし、地下鉄で友人とクレムリンへ赴くと、
赤の広場もクレムリンとホワイトハウスを結ぶ大通りもバリケードで塞がれていた。
しかしそこでは銃撃戦はなく、いかにもロシア的なお婆さんと学生っぽい青年が、
お互いの政治論を戦わせていたのでほっとさせられた。
しかし、数日後、テレビの画面に映った映像を見て驚愕した。
ホワイトハウスの上半分が黒こげになっていたのだ。
なんとエリツィンが自国の国会議事堂に砲撃したのだ!
私はロシア人を欧米の常識で決して判断しない。
あの朴訥(ぼくとつ)な人柄と
「ニチェボー(まあ気にすんなよ)」の気風は大好きである。
しかし、この砲撃にはさすがに開いた口が塞がらなかった。
通訳の方の友人は国会議員であったそうだ。
内戦の際、ホワイトハウス内にいたという。
短期間で解決した内戦ではあっても、戦(いくさ)…である。
犠牲者が生まれ、友人は哀しみに打ちひしがれる。
私は、ロシアの涙を生涯忘れない。
そして、わが青春のきらめく一ページとなったロシアの未来に希望を願う。
≪ロシア詩人チュッチェフの詩≫
ロシアは頭だけでは理解できない
並の尺度では計れない
ロシアだけの特別な体躯があるから
ロシアは信ずるしかない